年々難化している医学部に
1年で合格していただくため
03
03 2種類のカリキュラム

(1人1人に、年間カリキュラムと1回1回の授業ごとのカリキュラム)
年間カリキュラムと、そして、予備校の授業と同じ意味の1回1回の授業ごとのカリキュラムの2種類のカリキュラムになります。
●年間カリキュラム
教材、学習目標、学習方法などのカリキュラムです。
年間カリキュラムだけで、1教科、1科目で、A4の用紙2、3枚くらいになります。
●1回1回の授業ごとのカリキュラム
どのような分野をどのような順番でどれだけの回数で授業を進めていくかという、1回1回の授業ごとのカリキュラムを予備校側と講師が一体となって決めています。
2種類のカリキュラムで、全教科でA4の用紙15~20枚くらいになります。
予備校の指導方針を徹底させ、または、決まった時期までに決まった範囲を終わらせるため、というのは言うまでもありませんが、授業の質や学習効果を最大限上げるため、予備校と授業の担当講師が一体となって、学力診断テストと学力自己申告シート、そして、志望校などを元に、年間カリキュラムと、そして、予備校の一斉授業並みの1回1回の授業ごとのカリキュラムを1人1人に対して作成します。
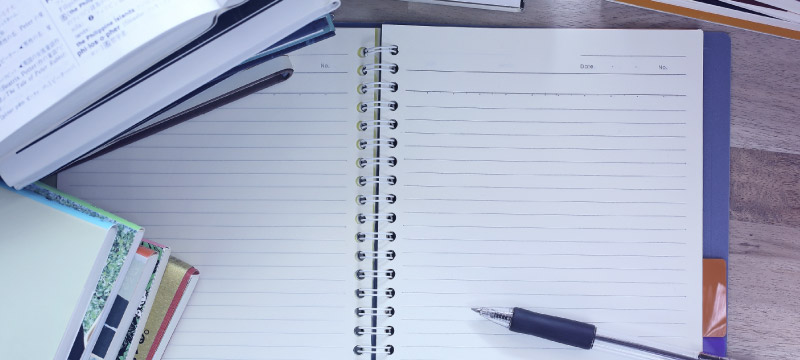
カリキュラム作成にあたり
☆
学力診断テストで学力レベルを診断
入塾時に受けていただく学力診断テストをもとに、苦手分野と得意分野、そして、それだけでなく、苦手な問題形式や得意な問題形式(英語であれば発音・アクセント、語彙問題、文法問題、語句整序、長文読解、和訳、英作文など、理科であれば知識問題、計算問題、論述問題、実験考察問題)なども含めて、学力のレベルを診断します。 学力診断テストの問題のレベル 基礎的な問題、共通テストレベル、そして、私立の医学レベルの問題を中心に、幅広い難易度の問題で構成されています。
☆☆
学力申告シート、も含めて合格するための戦略を作成
学力診断テストと過去の学習内容を記入していただいた学力自己申告シートを組み合わせて、合格するための戦略を作成します。
現在の学力が同じ場合でも、それまでの学習方法が違えば、合格するための戦略は当然違ってきます。
例えば、同じ苦手な状態でも、今まであまり学習していない場合と今まで学習している場合では、言うまでもありませんが、合格するための学習方法は異なります。
今まで学習しているけれども苦手な場合は、これまでの学習方法で、何がよくなかったのか、何が足りなかったのか、分析が必要になります。
分析および改善点の例
●例えば、問題が解けなかった場合に、解説を読んで理解できた状態で安心したことはないでしょうか。
理解できることと自分でもできることは、レベルが異なります。
理解できたことも、自分で解きなおすとできない場合もあります。
解きなおせばできる場合でも、必ず自分で解きなおしておかないと忘れてしまいます。
●例えば、解けなかった問題を解説を見ながら解いて、その状態で安心したことはないでしょうか。
普段解ける問題も、試験では解けないこともあります。
ですから、試験で解くためには、 普段なら確実にできるようにする必要があります。
そのためには、何も見ない状態で出来るようになるまで解きなおしましょう。
何も見ないよう状態で解けてその問題を初めて1回解いた、ですから、見ながら解いただけではその問題をまだ1回も解いていない、と考えていただくといいと思います。
実は、定着率を大きく上げるために、復習でさらに行うととてもよいことがあります。
これまでの学習方法の改善点を具体的に示し、より学習効果の高い予習や復習の方法を指導させていただきます。
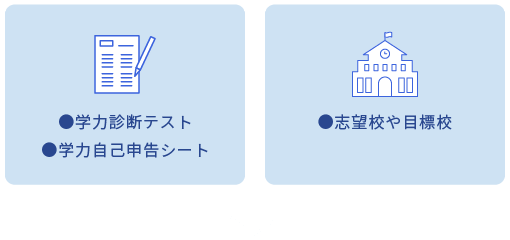
年間カリキュラムだけでなく、
予備校の1回1回の授業ごとのカリキュラムを、
1人1人に対して作成

